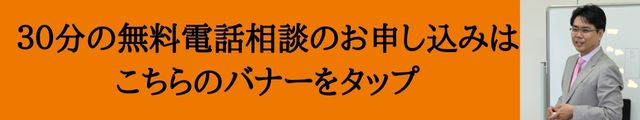飲食店でクレームを起こさないためにできる4つのポイント
2025年1月8日リライト
世の中全体的に、
クレームの数自体も増えている
気がします。
しかも
最近のクレームは多様化しており、
対応が困難なものも増えています。
今までクレーム対応について、
色々とこのブログで触れてきました。
起きたクレームは仕方ないとして、
2度と同じクレームを起こさないために
以下の4つのポイントを抑えてください。
目次
クレームを起こさないために
行動することが大切な理由
クレームを起こさないために
行動することはとても大切です。
なぜならかなりのメリットがあります。
クレームが起こらないことで、
- お客様の満足度が上がる
- 対応スタッフの心理的な負担の軽減
- クレーム対応時間が不要
に繋がることは確実です。
そして一番はクレーム対応に割く時間が
なくなることではないでしょうか。
クレームが解決しない間は、
どうしてもクレームに気持ちが行き、
日々のお客様対応に集中できなくなる
傾向があります。
カフェを始め飲食店において、
仕事は複雑多岐にわたるために、
少しでも減らすためにクレームは
もちろんない方が良いのです。
特に重度のクレームになれば、
責任者であるオーナーや店長が対応する
必要があり時間を割くことになります。
そのような状況になれば、
どうしてもクレームという後ろ向きな
ことに気持ちが行ってしまい、
売上アップという前向きの気持ちには
なりづらくなるのですよね。

クレームが発生すれば店長はその対応が最優先になります
画像はイメージ(写真ACより)
クレームが起こる前の予兆
クレームは起こる前に予兆があります。
クレームが1件あると、問題を抱えた顧客が他にも24人存在し、そのうち6件は非常に深刻な問題である。
ハインリッヒの法則より
上記の法則からわかるように、
クレームには予兆が存在します。
その予兆を感じ取るために、
日々の報連相を大切にしましょう。
もちろん毎日の日誌での報告も大切
です。
しかし一番は、
小さな問題でも報告し共有化できる
体制であるかということです。
人は悪いことほど、
報告できない傾向にあります。
だからこそ、
どんなに小さいなことでも、
すぐに報告・連絡・相談できる
体制作りが大切なのです。
クレーム対応はスピードが大切
なのです!
すぐにお店全体でクレームを共有
できる体制にしましょう。
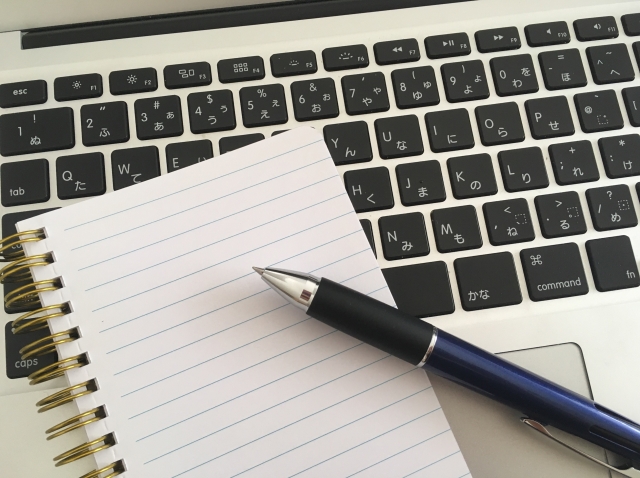
クレームを共有できるといいですね
画像はイメージ(写真ACより)
クレームを起こさないために必要なこと
クレームが起きる原因として、
事前期待>利用実感
の法則があります。
参考記事
カフェでお客様の顧客満足度を向上させることがなぜ大切なのか?
つまり、
「期待していたのに全くの期待外れの対応」
とお客様が感じたときにクレームが起こる
のです。
そうならないためにも、
以下の4つを抑えておきましょう。
顧客満足の向上の鍵はQCSの向上
断言します。
クレームを起こさなためには、
QCSのレベルの向上が全てです。
これは以前のブログでも
CS(顧客満足度) = Q(おいしさ) × C(きれいさ) × S(サービス)
と伝えているとおりです。
参照記事
QCSの掛け算があなたのカフェに対する顧客満足度である
日頃の研修やトレーニングを
QCSの向上のためには、
スタッフを育成することが
大切になります。
そのための方法として、
研修やトレーニングに参加
してもらうことです。
要は
スタッフに投資する
ということです。
わかっていても、
- 人がいなくて研修に時間を避けない
- お金に余裕がなくて研修に行かされない
ということありますよね。
スタッフに投資する
=お店のQCSをレベルアップ
顧客満足度の向上である
ことを忘れないでください。
顧客満足度が向上すれば、
当然クレームは少なくなり、
売上アップします。

クレームの本質を読み解く
クレームが起こったときに、
そのクレームにある本質的な問題に
向き合うことが大切です。
要は繰り返し同じクレームが
起こらないために根本的な原因
を突き止めることです。
例えば、
料理の中に髪の毛が入ったというクレーム
が発生したとしましょう。
このクレーム、
カフェを始めとする飲食業においては
あってはならないクレームの1つです。
2度と同じクレームを起こさないために、
根本的な原因を究明する必要があります。
そのために、
どのような経路で毛髪が入ってのかを
徹底究明する必要があります。
もしかしたら、
ユニフォームとしてキャップなどを導入
する必要があるかもしれません。
ユニフォームに付着した髪の毛が落ちた
かもしれません。
厨房のスタッフの中に、
髪の毛を触るクセがある者がいる
かもしれません。
原因を究明して
同じクレームが起きないように再発防止策
を実施することが経営者及び店長の務めです。

画像はイメージ(写真ACより)
起こったクレームを共有化する
クレームを共有化する
=お店に関わるスタッフ全員が知っている
ことです。
共有化するタイミングとして、
2つのタイミングがあります。
まず、
クレームが起こった瞬間お店全体で共有
していることが大切です。
それに加え、
その時いなかったスタッフも知っている
ことも大切です。
共有化するスピードもまた重要です。
素早くクレームを共有化するためには、
何をすべきでしょうか?
- オーナー、店長、責任者がすぐ知る体制にする
- クレーム報告書を作り全員が見れるようにする
- クレーム共有化ノートを作る
ポイントはお店のスタッフなら、
誰でも見ることができる場所に
あることです。
報告書やクレームノートには、
- クレームが発生した日時
- お客様の特徴(氏名がわかれば氏名)
- クレームが発生した時の状況
- クレーム内容
- どのように対応したか
- 解決済かどうか
が書いてあると良いでしょう。
このように、
クレーム内容をスタッフ全員で共有化する
ことで、
クレームを出してしまったお客様が
もし次の日に来店されたら、
「先日は大変失礼しました」
と素早く対応ができるのです。
参照記事
クレーム対応したお客様が再利用するために
クレームを起こしてしまったお客様が
また利用してくれるかどうかは
あなたのカフェのその時の対応次第です。
クレームは0にしようと思っていても
営業していれば発生してしまうことも
事実です。
クレームが起こってしまったら、
- 誰もが基本的なクレーム対応ができ、
- そのクレームの根本的な問題に気付き、
- 素早く店舗全体で共有化する
ことを心がけ次回の来店に繋げてくださいね。
クレーム研修やっております。
- 今までの20年以上にわたる私の現場経験
- 今でも現場に立ちオペレーション及び接客
- 通販会社でのクレーム対応責任者として年間600軒以上のクレーム対応経験
に基づくケーススタディが非常に多い内容です。
ご興味がある方は下記リンクよりご覧ください。
この記事を書いている人

- カフェコンサルタント
- コーヒー好き、カフェ好きの趣味が高じてカフェコンサルタントを始めて7年になります。このブログを読んだカフェ関係者が「これやってみよう」と思えるような売上アップや教育法を発信しております。簡単な質問は無料で対応しております^^
最新の記事
 カフェ管理項目2025年7月2日カフェ経営が難しいと言われる理由とそれを回避する仕組み
カフェ管理項目2025年7月2日カフェ経営が難しいと言われる理由とそれを回避する仕組み カフェ管理項目2025年6月25日孫子の兵法の「将の五徳」から得られる優れた経営者が備えるべき資質
カフェ管理項目2025年6月25日孫子の兵法の「将の五徳」から得られる優れた経営者が備えるべき資質 人材の採用、育成及び教育2025年6月18日カフェスタッフに指示を出しても伝わらない理由と指示の出し方
人材の採用、育成及び教育2025年6月18日カフェスタッフに指示を出しても伝わらない理由と指示の出し方 カフェ管理項目2025年6月11日カフェでテイクアウト商品を開発する際の手順と注意点
カフェ管理項目2025年6月11日カフェでテイクアウト商品を開発する際の手順と注意点
カフェ経営者に贈る日々の売上アップ法を配信
メルマガでは配信中です。
今ご登録いただくと
小冊子『カフェを始めとする小規模の飲食店がこれから生き残るための指南書』ほか、すぐにお店で使えるツールがダウンロードできます。
今すぐメルマガに登録して手に入れてください!